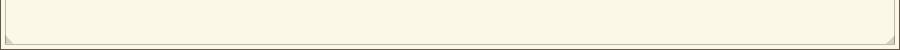『サード・パーソン』を観ながら、すぐに頭に思い浮かんだのが、ウディ・アレン監督・主演の『地球は女で回ってる』(97)のことだった。主人公は売れっ子の小説家で、周囲から孤立しかけている。というのも彼は、別れた妻たち、愛人、友人、家族のプライバシーをほとんどそのまま滑稽な小説の題材にしていたからだ。映画では、そんな主人公の現実の世界と虚構の世界が、別のキャストを使って対置するように描かれていた。 ポール・ハギスはより大胆な表現で、マイケルという作家の複雑な世界を掘り下げている。この映画では、現実と虚構の区別が判然としない。それは、人間としてのマイケルと作家としてのマイケルの境界が揺らいでいるからだ。彼は過去の辛い出来事に対する心の整理がつかないまま、新作を執筆している。つまり、迷いがあり、作家としての欲望に忠実になれない。そんな彼は、三つの物語を通して過去を清算すると同時に、欲望の赴くままに新作を書き上げる。
![]()
非常に複雑な物語だ。
正直、この原稿を書いている今でさえ自分の解釈に絶対の自信があるかと言われたら微妙だ。しかしちょっと聞いて欲しいのよ、俺の感想と解釈を。
実在する人物は3人だけ。
僕はこう思う。作家のリーアム・ニーソン、その妻のキム・ベイシンガー、愛人のオリヴィア・ワイルドだけが実在の人物であると。その他の人物はリーアム・ニーソンが手がける小説の登場人物達だ。
ミラ・クニスとジェームズ・フランコの息子=オリヴィア
オリヴィアの幼少期の出来事をリーアムが小説にするにあたり娘ではなく息子に書き換えた。
ジェームズ・フランコが息子に対して異常に執着している事と現代で登場するオリヴィアの愛人ダニエルが実の父親だった事からもこの繋がりは間違いないように思う。息子の名前が「ジェシー」なのもヒントだよね。結果、世間の目を気にしていたオリヴィアは幼少期から性的虐待を受けていた人物である事が小説でバラされてしまったんだと思う。
リーアム=エイドリアン・ブロディ。キム=マリア・ベロ。
ここでもリーアムが失った息子はエイドリアン・ブロディの8歳の娘と書き換えられた。
エイドリアン・ブロディとマリア・ベロの電話での会話からもリーアム・ニーソンとキム・ベイシンガーの関係を描いている事が分かる。
それじゃモランとその娘の事件はなんだったのか。
…分からねえ…そこが分からねえ…ただ編集者が「人生の言い訳をしているような小説」と評価したストーリーがこれなんじゃないかと思う。“娘を救えなかった男が女と出会いその娘を救って素敵なシャツで旅に出る”というある意味チープな物語がこのパートなんじゃないだろうか。消えていく車の後部座席には小さい子供がちゃんと乗っているしハッピーエンドになってるのも微妙にチープだ。
リーアム・ニーソンは群像劇を書き上げた。
「新作執筆中に方向性が変わった」と言ったのは大きなヒントに思う。エイドリアン・ブロディとモラン・アティアスによって描かれる“娘も恋もゲットだぜ!”という話を書いてるうちにミラ・クニスとジェームズ・フランコの“変質的な父親の愛”も盛り込んだ新作が仕上がった、というのが僕の解釈だ。
みんなはどう思ったのかしら。是非知りたい。そしてもう一度「サードパーソン」を観る時に僕の解釈の検証もお願いしたい。
是非、よろしくお願いします。
![]()

一度観ただけではスッキリさせてくれない意地悪さが素晴らしい!答えがあるようでないということなのか、答えがたくさんあってそのなかから観た人に選んでくれということなのか、観る側に選択の余地を多く与える作品だと思います。わかりやすい映画も良いけれど、こういう哲学的なテーマをともなうストーリーで、物語の構成を理解するにも頭を使う映画は、観た後、日を増すごとにおもしろさが自分のなかで膨らみます。
![]()
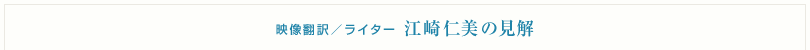
パリ、ローマ、そしてニューヨーク。魅力的な都市のはずなのに、そこにいる男女はずっしりと肌に沈むような重い空気の中、ピリピリと焦燥感を抱いて歩いている。風船のように宙に浮かんだ心が、どこかへ飛んでいってしまわないように、ヒモの先をギュッと握り締めているようだ。そして女性たちは“彼”に、“Watch me (見ててね)”という言葉を投げかける。
“事実は小説より奇なり”というものか。小説家マイケルは、“彼”の物語を自分の体験を通じてしか語ることができない。だがアンナへの愛情は、まったくのウソだったとは思いたくない。執筆のための刺激薬だったにせよ、彼女を見る目に戸惑いが滲んでいるように思う。左の薬指を見れば、“The one(生涯唯一の愛)”ではないことは分かるけれど。きっとこれまで感情に左右されずに生きてきたから、悲しみと罪悪感をうまく受け入れることできないのだ。それゆえにアンナではなく、小説家の“彼”を選んでしまったのかもしれない。
“君の人生の言い訳でしかない”という出版社の友人の言葉どおり、ローマやニューヨークの物語は、マイケルの弁明だ。だが、スコットとモニカの笑顔のドライブや、リックのジュリアへの電話は、マイケルが一筋の光を探し求めていたからではないか。
マイケルがアンナのことを書くのは、最後の選択だった。さまざまな重圧から解き放たれるために、彼女の弱さを利用したのだ。彼女の心を引き裂くことが、読者の心を魅了する“彼”に必要だった。それが“彼”にとって“最高の選択”だったのだ。
・・・と考える人は、次のアンナになるかもしれませんね。
瞬きをするのがもったいないほど、緻密なシーンの押収。『マルコビッチの穴』のように、ポール・ハギスの頭の中に入る穴があれば、足を踏み入れてみたいような、みたくないような。
ところで、感情のないマイケル(リーアム・ニーソン)より、悲壮感たっぷりのエレイン(キム・ベイシンガー)を恐ろしく感じたのは私だけではないはずです。笑
![]()
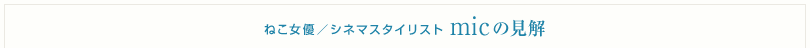
大人になると厄介な事が沢山ある。
自分で自分の事がわからなくなったり真剣であればあるほど、想いとは別の、負のスパイラルに陥ったり。
急に無謀になったかと思えば、何かを執拗に守ろうとして、
大切な人を裏切り、裏切られ、傷ついて、、、。
大人になると、もっとスマートに生きられると思ったのに、なんで、こうもややこしくなっちゃうんだろ。
本作に登場するのは、そんな愚かさを抱えた男たちと、ある意味どうしようもない女たち。
救いなのは、彼らが愛を求めて交わった時、人生の道をほんのわずかでも前に進んでいるということ。
ポール・ハギスは、決してわかりやすいハッピーエンディングになんてしないけど、あのエンディングの意味を考える事が、本作のもうひとつの楽しみのようにも思えるし、何より、自分がこじらせ女子だと認識している人(=私)にとっては、自分を心から愛せなかった3人の女達が一歩踏み出す姿に勇気をもらえる気が致します…。
![]()
3つの街、3組の男女の物語がだんだん交錯していって、最後にまとまる。そこまでは、誰もが想定内だろうけど、本作のラストは、完全に想定外のものだった。え!?そう来た?脚本の名手ポール・ハギズは、どうやら50回くらい草稿を書いて、設定を練りに練って、たっぷりと熟成したものを、ようやく監督したらしい。なるほど、これは、ぽっと出の作家ができる技ではない。トルネードですよ!ストーリーテリングの新しい方程式というか、一歩、進化した形を見せてくれた感じ。見終わった後、リピートしたくなるところも、ニクイなあ。
![]()
ファンタスティックな仕掛けで三都市のエピソードが交錯し、絡み合いながら ひとつの物語となるミステリアスなロマンス。 “娘に会いたい”ローマのエピソードと“息子に会いたい”NYのエピソードは、 “子供を失った”悩める小説家マイケルが生み出したフィクション? スランプの末に上梓した新作は、目を離して亡くした子供への贖罪のつもりか。 愛する人を裏切ってなお叶えたかった、彼の表現者としてのエゴイズムにくらくら。 自分だけカタルシスを得たに違いないマイケルは、ハギス監督の分身だろうか。 「Watch me」という言葉を反芻しつつ、もう一度最初からじっくり観たくなる。
![]()
人間は愚かだけれど、愛おしい存在。「ウォッチ・ミー」との内なる声に耳をすます。愛の戯れがあり、憎しみがある。嘘もあれば、裏切りさえも。迷宮のような愛の種々相から立ち上がるのは、人間の真実。ポール・ハギスの内なる声に、耳をすまし、映像に身を委ねると、愚かだけれど愛おしい人間の、真実の愛が見えてくる。必見。
![]()

はっきり言って、ストーリー自体はよく分からなかったです。特に3つのエピソードの関係性は。だから解釈のしようがない。ですが、それをつなぐ演出には工夫が凝らされていて、ディテールはとても面白いと思いました。映画史とは、CGや3Dも含めて観客が自然に、違和感を覚えることなくストーリーに埋没できるための技巧を突き詰めていく歴史だったと言えるでしょう。例えば「編集」自体が嘘ですが、その嘘を気取られないための。ポール・ハギス監督は、3つのエピソードをつなげるために、共通のイメージを使って「編集」の違和感を消していきます。水、自動車、ケータイ、女性が服を脱ぐ動作…。特に水のイメージの連鎖は素晴らしく、最後にはそれが物語とも密接に結びついていることが分かります。彼にはどうしても“脚本家”というイメージがつきまといますが、“監督”としても頑張っているのです。もちろんキャストも、女優陣がよく頑張っています。
特にオリヴィア・ワイルド。間違いなく彼女の飛躍作になることでしょう!
![]()
ハギス監督の代表作『クラッシュ』は、全世界のゲイに愛された、カウボーイ萌えシーンあり問題提起ありの名作『ブロークバック・マウンテン』のアカデミー作品賞受賞を阻止したにっくきライバル…のはずだったんですけど、これもホントに良い映画だったのよねぇ。
多民族国家アメリカを舞台に、差別と憎しみ、時にそれを超える愛や奇跡が登場人物たちを複雑に巡る物語。この作品で、ハギス監督が群像劇のキャラ役割というものをムダなく緻密に描ける天才だというのを思い知ったんですけど、今作はその変化球版。
群像劇の舞台は多民族国家ならぬ多人格作家、とでも言いましょうか。別にリーアムたん演じる主人公が多重人格というわけではないんですが、作家なんてものは多数のリアリティある人格を脳内に作り上げられてナンボ。だからこそ周囲のリアルな人間たちも、彼の表現欲求のネタとして消化されていくだけ。
多民族を抱える国家の問題と同様に、彼自身も、大物作家としての彼、子を失った父親としての彼、傷ついた女を愛する男としての彼、という、エヴァンゲリオンのMAGIシステムのような三権分立アイデンティティに陥っていたと思われます。
そんな彼が起死回生の作品に選んだのは、この三つの自分全てを作品化して発表すること。虚構と現実が入り混じる描写は、謎と混乱を生みがちだけれど、そもそも映画自体が(主に)フィクション表現であり、大物脚本家のハギス監督の立場から生み出された今作ってのは、その構造自体が立体的なのよね。
>イヤミなほどに知的で後をひく作り。煙に巻かれて何がリアルなのかも見失いそうなアタシは、一番の生々しいリアルを感じられたリーアムたんのゆるふわボディを思い出して、悶々とするしかないんだわ…。
![]()
ツイッターでのご投稿の際は、#サードパーソンをつけて投稿してください。
ご投稿いただきましたコメントは、公式SNS、広告などに使用させていただく場合がございます。
Facebookでの投稿はこちらからお願いいたします。
投稿には、Facebookアカウントにログインしている必要があります。